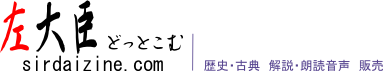思ひわびさても命はあるものを 憂きに堪へぬは涙なりけり 道因法師
おもいわび さてもいのちは あるものを うきにたえぬは なみだなりけり (どういんほうし)
意味
つれない人を思って嘆き悲しみ、それでもなんとか生きながらえているのに、つらさに堪えきれずに涙が流れ落ちてしまうよ。
百人一首の全音声を無料ダウンロードできます
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
語句
■思ひわび 自分に対してつれない人を思い、嘆き悲しむ。複合動詞。和歌ではほとんどが恋歌に用いられる。 ■さても 副詞「さて」+強めの「も」。まとめて副詞と見る。そのような状態でも、やはり。 ■命はあるものを 「は」は係助詞。他と区別する意。下の「涙」が辛さに堪え切れないで流れ落ちるのに対し、辛い中にもなんとか堪えて、命は存在している(生きながらえている)の意味。「ものを」は逆説の接続助詞。 ■憂きに 堪えきれない。形容詞「憂し」の連体形+格助詞「に」。■堪へぬ 「絶えぬ」説。「絶えぬ」「堪えぬ」の掛詞説もある。 ■涙なりけり 「なり」は断定の助動詞の連体形。「けり」は初めて気付いた感動を意味する終助詞。
出典
千載集(巻13・恋3・818)。詞書に「題しらず 道因法師」。
決まり字
おも
解説
自分の意思ではおさえられない恋心を、「命」と「涙」を対比させて詠んだ歌です。悲しみの中にも、それでも命はなんとか存在している、つまり生きながらえているのに、涙はとめどなく流れてくる。こればかりは、どうにもならない。しみじみとした嘆きを、相手に訴えかけているのです。
道因法師(1090-没年未詳)。俗名藤原敦頼(ふじわらのあつより)。祖父は対馬守藤原敦輔。父は治部丞藤原清孝。従五位下右馬佐に至るも80過ぎの1172年出家して道因と名乗ります。
数々の歌合せに参加し、自らも「住吉社歌合」「広田社歌合」などの歌合せを主催しました。
はだし右馬佐
道因が藤原敦頼といった出家前、従五位下右馬佐として崇徳院にお仕えしていました。右馬佐とは朝廷に献上された馬の飼育・調教にあたる右馬寮(うめりょう)の次官のことです。
保延4年(1138年)朝廷の右馬寮で馬の飼育をとりおこないました。その任務を終えると、先例にしたがって衣装を下仕えの馬飼いどもに与えることになっていました。高価な衣装だったのです。しかし敦頼は、
「これはしばし借りておく。後日、値を取りに来い」
「えっ…。しかし、お役を終えた後は衣装を貰い受ける習慣になっていますが…」
「わかっている。後日、値を取りに来るがよい」
敦頼はこう言ったまま日数が過ぎました。
「なんだいあの長官は、いつまで待っても衣装が下されないじゃないか」
「騙された…」
馬飼い供は、大いに敦頼を恨みました。
翌年、敦頼が伊勢の斎宮の行列のお役について一条大路をしずしずと過ぎていった時、かの馬飼いどもと思いもかけず出あわせます。
「あっ!装束どうなったんですか」
「装束」「なあなあにはすませんませんよ」
「ま、待てお前達、落ち着け。今は大事なお役の途中…
うわあっ」
いきり立った馬飼たちは、敦頼の衣冠・下着・帯まで剥ぎ取ったので、敦頼はどうしようもなく、赤裸で逃げ出しました。
「うわーっ、何なんですかあの人は?」
「馬佐(うまのすけ)だそうです」
「じゃあ、さしずめ、はだか馬佐といったところですな」
人々は大笑いしました。
その後剃髪して道因と名乗りますが、道因は歌の事にはとても執着が深く尋常ではありませんでした。歩いて住吉神社へ月参りし、「どうか七十、八十までよい歌を詠ませてください」と熱心に祈りました。
ある歌合に、藤原清輔が判者をして道因の歌を負けとしたところ、わざわざ清輔の館まで来て切々と泣いて恨み言を延べるので、清輔は困ってしまいました。
「歌について、あれほど大変な目にあったことはありません」と人に語ったとか。
歌の会の時は講師(こうじ)のもとに寄って熱心に集中して聞き入るさまは、尋常のことではありませんでした。
俊成の夢枕に立つ
藤原俊成が後白河法皇の勅命を受けて『千載集』を編纂したのは道因法師の死後のことでした。「歌の道に志深い御仁であった」そう言って俊成は道因の歌を18首入れました。
すると夢の中に、
「俊成殿、俊成殿」
「う、うーん…。あっ、あれっ、あなたは道因法師さま」
「いかにも私は道因法師です。俊成殿、なんとお礼を申し上げて
よろしいやら。私の歌を18首も。よよよ…嬉しいやらありがたいやら」
はっと目が覚めた俊成はいよいよ、あはれに思い、さらに2首を足して20首としました。
ある時藤原忠実公(76番忠通の父)が、近江国の鏡宿の遊女を召して歌を歌わせました。すると遊女たちは、源俊頼の歌を歌います。
世の中は憂き身に添へる影なれや 思い捨つれど離れざりけり
(世の中はこの悲しい身により添っている影なのでしょうか。
俗世への執着を捨てたとは思っていても、やはり捨て切れません)
「ほう。俊頼の歌はこんな所でも歌われているのか。さすが。
歌人のほまれよのう」
感心する忠実。
この話を永縁僧正(ようえんそうじょう)という僧が聞いて、うらやましく思います。
(歌人のほまれなら、わしとて負けぬ)
聞くたびにめずらしければ郭公
いつも初音の心地こそすれ
(聞くたびにほととぎすの声は新しいあはれを感じる。
いつ鳴いても初音のように思えるのだ)
永縁僧正はこの歌をたくさんの琵琶法師たちに教えて、褒美を取らせた上で語らせました。
それを聞いて今度は道因法師が、
「なんだ、それなら俺だって」
盲人たちを集めて、褒美は何も与えず、わが歌を歌え、歌えと
強引に歌わせようとしましたが、誰も歌うものはいませんでした。
道因法師の歌への執着のなんとすごきことよと、人々は笑いあいました。