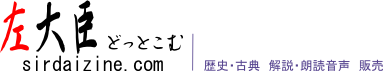寂しさに宿を立ち出でてながむれば いづくも同じ秋の夕暮れ 良暹法師
さびしさに やどをたちいでて ながむれば いずくもおなじ あきのゆうぐれ (りょうぜんほうし)
意味
寂しさに耐えかねて家を出ると、そこらじゅう、どこも同じように寂しい、秋の夕暮れだよ。
百人一首の全音声を無料ダウンロードできます
【無料配信中】福沢諭吉の生涯
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
語句
■さびしさに さびしさのために。さびしさに耐えかねて。「さびしさ」はシク活用形容詞の終止形(または語幹)に名詞を作る接尾語「さ」がついたもの。「に」は原因・理由を意味する格助詞。 ■宿を立ち出でて 「宿」は作者が住んでいる草庵。字余りが「思わず宿を出た」勢いを表している。 ■ながむれば 動詞「ながむ」の已然形+接続助詞「ば」で順接の確定条件。「ながむ」はぼんやりと物思いにふける。9番小野小町参照。 ■いづくも同じ 「いづこ」とする本文もあり。「いづく」を連体形と見て下の「秋の夕暮れ」に続くという説と、終止形と見てここで切れる説がある。 ■秋の夕暮れ 体言止め。『後拾遺集』からよくみえ始めた言葉で『新古今集』には特に多い。多くは結句に用いる。西行法師、寂蓮法師、藤原定家の三夕の歌が有名。
出典
後拾遺集(巻4・秋上・333)。詞書に「題しらず 良暹法師」。第四句を「いづこ」とするものもあるが古い写本や『百人秀歌』でも『後拾遺集』でも「いづく」が多い。
決まり字
さ
解説
特に技巧も無く、スッと素直に入ってくる歌です。秋の夕暮れの寂しさに、どうにもいたたまれない気持になり、タタッ…と面に駆け出してみると、どこもかしこも、秋の夕暮れの景色だった。
第二句が「立ち出でて」と字余りになっている所が、いかにも思い余って駆け出した感じが出ていて、勢いがあります。
秋の夕暮れを歌に詠むことは後拾遺集にはじまり古今集ではさかんになりました。有名な三夕の歌は、学校で必ず習いますね。
さびしさはその色としも無かりけり 真木立つ沢の秋の夕暮 寂蓮
心なき身にもあはれは知られけり 鴫立つ沢の秋の夕暮れ 西行
見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとま屋の秋の夕暮 定家
良暹法師。生没年未詳。山城国愛宕郡(おたぎのこおり 八瀬村の北)に出生で父は不明ですが、母は藤原実方の家の女童白菊という人だったと言われます。比叡山の僧で、祇園社(現 八坂神社)別当となり、晩年に隠棲したと伝わっています。
朧の清水
良暹法師が大原に住んでいた頃に「良暹法師大原に籠り居ぬと聞きて遣しける」と詞書して素意(そい)法師との歌のやり取りが伝わっています。
素意法師
水草ゐし朧の清水そこみすて 心に月のかげは浮ぶや
(水草が生えている朧の清水ですが、その水底は澄んでいるように、あなたの心にも月の姿が浮かんでいるでしょうか)
良暹法師の返し。
良暹
程経てや月の浮ばん大原や朧の清水すむ名ばかりぞ
(私の心に月が浮かぶには、まだ時間がかかりそうです。大原ですねえ。朧の清水が澄んでいるというのは、その名ばかりですよ)
朧の清水は大原寂光院に通じる細い道沿いに、潅木の下にある湧き水です。現在石碑が建っています。
建礼門院徳子は、壇ノ浦の合戦の後、尼となり、大原の地に移ってきましたが、途中このあたりで日が暮れてしまいました。その時、朧月夜の光に照らされて、清水にご自分の姿が映りました。
そのやつれ果てたお姿をご覧になり、建礼門院はああ…と嘆かれたということです。建礼門院はたいへんな美人だったため、身の衰えがよりいっそうこたえたのです。
大原やいづれ朧の清水とも 知られず秋はすめる月かな 兼好法師
春雨の中におぼろの清水かな 与謝蕪村
物乞いの歌
良暹が大原に住んでいる時、伏見の知人のもとに食料・物資を乞うための手紙に書き添えた歌、
大原やまだすみがまもならはねば 我が宿のみぞ烟たえたる
(大原に住み始めてまだ慣れないので、ここは炭を焼くところですが、私の宿のみは焼くものもなくて竈の煙が絶えています)(→貧乏です。食料・物資をめぐんでください)
この歌を踏まえて、後年東山の木下長嘯子(1569-1649)が知人安楽庵策伝(あんらくあんさくでん)のもとに借金を乞う手紙の奥に、歌を添えました。
この頃の宿の烟ぞまづ絶ゆる つひの薪の身は残れども
(最近、宿の煙りが絶えてしまっている。いつまでも火を燃やし続ける薪のようなこの身だけは残っているのに。だから、金を貸してくれ)
ほととぎすの歌で恥をかく
また良暹はすぐれた歌人でしたが、ほととぎすの歌を詠み誤ったことがあります。
『袋草子』には名人にも失敗はある、良暹は郭公ながなくという歌の句を、郭公が長く鳴くと間違って理解していたとあります。
橘俊綱の館で五月五日、ほととぎすを歌に詠みました。
宿近くしばしながなけ時鳥 今日のあやめの根にもくらべん
(宿の近くでしばしの長い間鳴いてくれほととぎすよ。
五月五日のあやめの根にも比べられるほど、長く鳴いてくれ)
同席していた懐円という歌人が、これをバカにして言いました。
「ほととぎすが長く鳴く?ほとーーーーーーーーーー
……とぎす。とでも鳴くのですかな」
これは古今集の歌に、
時鳥ながなく里のあまたあればなほ疎まれぬ思ふものから
(ほととぎすよ。お前は確かにいい鳥だが、あちこちの里で鳴く浮気者で私だけの者にはならない。だからやはり好きにはなれないのだよ)
とあるのを踏まえたつもりの歌でした。本歌の「ながなく」は「汝が鳴く」であるのを、良暹は間違って「長鳴く」と理解しており、恥をかいたのでした。こんな失敗もあったのです。
「関の石門」でやりこめられる
『袋草紙』には別の失敗談も語られています。良暹がある所で人に語って言うことに、ある日近江から京都へ向かう途中、逢坂で時雨にあった時、良暹は石門(いわかど)に賢くも立ち入って、濡れなかったということです。
「さすが良暹どの、風流ですなあ」
周囲は感心していましたが、懐円が言います。
「へえ。石角にどうやって立ち入られたのですか。どんなふうに門があったのですか?」
「それは…ぐぬぬ」
良暹は言葉につまってしまいました。
実は「石門」という言葉は石の門ではなく、石がけわしく敷き詰めている地形を言うのでした。門や屋根があるわけではないのです。だから石門に立ち入って雨をしのいだという話は完全な作り話でした。
良暹は懐円によって、このようにたびたびやりこめられました。
ただし源為仲(源為朝の兄。為義の子)の歌にも
あづま路のことづてやせんほとゝぎす関の石門今ぞ過ぐなる
(東路のことを、お前の伝えようほととぎすよ。関の石門を今こそ通り過ぎたよと)
とあり、この歌は「石門(いわかど)」を「石の門」と思っているようです。しかし懐円の指摘は正しいのでした。
逢坂の関の石門踏みならし 山立ち出づる霧原の駒
(逢坂の関のけわしい石の角を踏み鳴らし、山に立ち出る霧原の駒の早足)
こう詠んだのも、「石門」はけわしい石の角の意味で、「石の門」などという解釈は、間違いです。良暹は、懐円によってやり込められた形です。
大原の庵の跡
こんな話も伝わっています。
ある時源俊頼が友人たちとともに大原の地に馬に乗って遊びに行ったところ、俊頼がいきなり馬を降り、ひざまづきました。
「どうなさったのです?」
友人たちが驚いていると、俊頼は言いました。
「ここはかつて良暹法師の庵があった所です。
どうして馬に乗ったまま通り過ぎることができましょうか」
「おお…!」
俊頼の言葉を聞いた友人たちも馬から降り、皆でひざまづいたという話です。
良暹法師の住んでいた庵には、ある僧の言うことには障子に歌が書き付けてありました。
山里のかひもあるかな時鳥 ことしも待たで初音聞きつる
(山里なだけはあるなあ。時鳥よ。今年も待たされることなく、早めにお前の初音を聞くことができた)